過去の図書館劇場(平成19年度)(県立図書情報館館長公開講座)
図書情報館では、昨年度、 「館長公開講座 図書館劇場」と銘打ち、平城京を巡る歴史から、奈良の国際性や現在では忘れられている先進性や原風景を明らかにしました。
今年度は、『吉野絵巻』をメインテーマに、館長による講演、専門家による講演と関連書籍の朗読とで構成する図書館劇場Ⅱを開催します。
なお、本公開講座は毎回、奇数月の第4土曜日の13:00〜16:00に開催します。
今年度から開始時間が13:00〜になっています。ご注意ください。
- 図書館劇場Ⅱ(県立図書情報館館長公開講座) 第六幕
- 図書館劇場Ⅱ(県立図書情報館館長公開講座) 第五幕
- 図書館劇場Ⅱ(県立図書情報館館長公開講座) 第四幕
- 図書館劇場Ⅱ(県立図書情報館館長公開講座) 第三幕
- 図書館劇場Ⅱ(県立図書情報館館長公開講座) 第二幕
- 図書館劇場Ⅱ(県立図書情報館館長公開講座) 第一幕
図書館劇場 Ⅱ(県立図書情報館館長公開講座)第六幕「千秋楽」
第六幕は「谷崎潤一郎の吉野」をテーマに開催しました。また、「天地響命(てんちきょうめい)」 −中国古箏と打楽器・中国木琴による野外コンサートを開催しました。

画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、724KB]
- 主催
- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会
- 日時
- 平成20年3月22日(土) 13:00 〜 16:30
- 会場
- 庭園 および 1階 交流ホール
- テーマ
- 「谷崎潤一郎の吉野」
- 第1部(13:30〜14:20)
-
「天地響命(てんちきょうめい)」−中国古箏と打楽器・中国木琴による野外コンサート
演奏者 : 姜小青(ジャン・シャオチン/中国古箏)、 馬平(マア・ピン/打楽器・中国木琴) - 第2部(14:35〜16:30)
-
- 「吉野と柿の葉寿司」 田中 郁子氏 (株式会社柿の葉すし本舗たなか代表取締役社長)
- 「谷崎潤一郎を吉野に惹きつけたもの」 千田 稔(当館館長)
- 参加者数
- 約150名






姜小青(ジャン・シャオチン)

幼少の頃より古箏の英才教育を受ける。中国少年民族楽器独奏コンクールで第一位、金賞を受賞し。15歳で中央音楽学院(大学)に入学。 古牢五大流派の伝統演奏を修得する。来日後、坂本龍一氏のアカデミー音楽賞受賞作品「ラスト・エンベラー」のサウンドトラックに参加、 同氏の国内コンサートやアメリカコンサートツアーにも同行し、高い評価を得る。以後、東京を拠点に日本各地で多くの重要なコンサートに出演。 海外公演もたびたび行う。近年では、03年、第16回「JAL萬福寺音舞台」でソプラノのサラ・ブライトマン、ピアノのユンディ・リーと共演、 04年8月にはイタリアのカタ一二ア国際音楽祭で、城ノ内ミサ作曲「幻華〜古箏のための協奏曲」のソリストを務め、絶賛された。 また、05年、サラ・プライトマンの来日コンサート、アメリカのサンフランシスコ古箏協会第23回コンサートに出演、06年には日中コリアの 琴演奏家グループ「琴姫」の2月アメリカ公演、3月ロシア公演に参加し、いずれも大成功を収めた。 ラジオ・テレビ出演も多数。「ユニット悠風」を率い、「エイジアンファンタジー・オーケストラ」「六華仙」「天平楽府」のメンバーでもある。 他に、90年から2OOO年までサントリーウーロン茶のTV-CMで訳詞・歌・演奏も担当した。 (http://homepage3.nifty.com/jiang/)
馬平(マア・ピン)
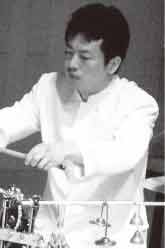
幼い頃よりピアノを学び、10歳から打楽器を始める。中央音楽学院卒業後、「中国交響楽団」に入団。1985年、 全国優秀音楽作品コンクールで優秀演奏賞受賞。在団中に行った全米公演で高く評価される。88年来日。東京芸術大学大学院で有賀誠門氏に師事。 94年、同大学修士課程修了。現在、打楽器アンサンブル、オーケストラ、中国民族音楽等、ジャンルを問わず幅広く活躍中。 西洋の打楽器、中国の打楽器ともにこなし、日本では唯一、中国でも数少ない中国木琴の演奏者としても貴重な存在である。 日中韓の琴演奏家グループ「琴姫」で打楽器を担当し、06年3月ロシア公演にも参加。「ユニット悠風」「天平楽府」のメンバー、 東京バッハ・カンタータ・アンサンブル」のレギュラーテインバニー奏者でもある。NHKの音楽番組にたびたび出演するなどテレビ出演も多く、 90年からはサントリーウーロン茶のCMで歌も歌っている。曲の意図するところをすばやくつかみ表現する感性の豊かさは、 どのアンサンブルでも信頼が厚い。
田中 郁子 (たなか いくこ)
奈良県生まれ。株式会社柿の葉すし本舗たなか、専務取締役を経て、代表取締役となり現在に至る。
図書館劇場 Ⅱ(県立図書情報館館長公開講座)第五幕
- 主催
- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会
- 日時
- 平成20年1月26日(土) 13:00 〜 16:00
- 会場
- 1階 交流ホール
- テーマ
- 「天誅組と吉野の近代」
- プログラム
- 参加者数
- 約200名



3F ふるさとコーナーにて、「天誅組をよむ」とのテーマで、![]() 関連図書資料の展示 をおこないました。
関連図書資料の展示 をおこないました。
野村 幸治
「維新の魁・天誅組」保存伝承・顕彰推進協議会事務局長、高取町観光ボランティアガイドの会事務局長
舟久保 藍
「維新の魁・天誅組」保存伝承・顕彰推進協議会特別理事、草莽義挙再探求会副代表
草村 克彦
「維新の魁・天誅組」保存伝承・顕彰推進協議会特別理事、草莽義挙再探求会代表
福井 正三
「維新の魁・天誅組」保存伝承・顕彰推進協議会幹事長、五條市シルバー人材センター理事長
阪本 基義
「維新の魁・天誅組」保存伝承・顕彰推進協議会副会長、東吉野村教育委員会教育長
図書館劇場 Ⅱ(県立図書情報館館長公開講座)第四幕
- 主催
- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会
- 日時
- 平成19年11月24日(土) 13:00 〜 16:00
- 会場
- 1階 交流ホール
- テーマ
- 「南朝悲史」
- プログラム
- 参加者数
- 約200名

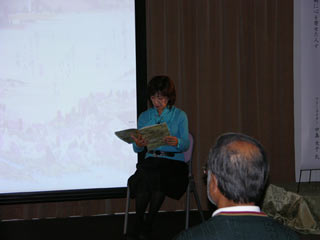

中島 史子
1949年 佐賀県生まれ
1970年 福岡県筑紫女学園短期大学国文科卒業
1979年 奈良市内に転居
1981年 奈良市地元情報紙に執筆を始める
1984年 大阪市内での情報紙発刊に携わる
1985年 奈良市地元情報紙に戻る
1987年 情報紙編集長
1990年 フリーとして独立 「なら大好き」などの編集執筆
1990年〜92年 朝日新聞奈良県版に「大和の古寺の女たち」を連載
1993年〜95年 朝日新聞奈良県版に「青垣いま模様」の連載
1994年 「大和の古寺の女たち」を出版(かもがわ出版)
1997年 「奈良花の名所12カ月」を出版(山と渓谷社)
1997年〜 近鉄ケ−ブルネットワーク発刊「ネットプレス」編集執筆
1998年 「中国花の名所12カ月」を出版(山と渓谷社)
2001年〜2004年3月 奈良県政だよりに「奈良ではじまった」を連載
2001年〜2003年 月刊誌「旅の手帖」に歳時記などを連載
2002年 NHKラジオ深夜便でお水取りの対談
2003年 民族芸術学会総会で「正倉院展添え釜にみる市民の芸術活動〜シルクロードのガラスとワインの茶会を事例として〜」の研究発表
2003年 NHKわくわくラジオで奈良のレポーター
2004年 東京国立博物館運営委員、奈良国立博物館評議委員
2005年 飛鳥保存財団評議委員
現在、歴史、文学、花などをテーマに執筆中。民族芸術学会会員
図書館劇場 Ⅱ(県立図書情報館館長公開講座)第三幕
- 主催
- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会
- 日時
- 平成19年9月22日(土) 13:00 〜 16:00
- 会場
- 1階 交流ホール
- テーマ
- 「西行と桜」
- プログラム
- 参加者数
- 約200名




前 登志夫
大正15年(1926)奈良県吉野郡生まれ。
20代の頃は主に現代詩を書き、柳田国男、折口信夫の民俗学を研究。
「再び自然の中に人間を樹(た)てる」というテーマをかかげ、昭和30年(1950)頃より郷里の吉野山中の生家に定住する。
郷土大和の先輩、前川佐美雄に親しみ、その影響を受ける。晴耕雨読の生活を基本として、独自の歌風をひらく。とりわけ、人間と自然との交霊や、宇宙的な反響によって、
存在の意味を問う形而上学的な抒情には定評がある。『山霊の詩人』『当代随一の韻律』『吉野の山人』『今 西行』などとよばれた。
歌と民俗の研究集団「山繭の会」主宰。季刊「ヤママユ」発行。
大阪金蘭短期大学教授(1974〜1996)。
昭和53年(1978)、第12回迢空賞をはじめ、平成10年(1998)、読売文学賞など多くの賞を受賞。平成17年(2005)6月、日本芸術院賞あわせて恩賜賞を受賞。
同年11月より日本芸術院会員。
自然を友とする山暮らしをつづけ、「吉野の仙人」などと呼ばれているが、80代になっても、現代日本の短歌界を代表する巨匠として執筆の日々を続け、
おりおりは講演や講義に都市へ出かけている。
川上小学校・中学校をはじめ、地域の魅力をよみこんだ校歌も多数作詞している。
- 著書
-
- 詩集
- 「宇宙駅」
- 歌集
- 「子午線の繭」、「霊異記」、「縄文記」(第12回迢空賞) 「樹下集」(第3回詩歌文学館賞)、 「鳥獣蟲魚」(第4回斎藤茂吉文学賞)、 「青童子」(読売文学賞)、 「流轉」(現代短歌大賞)、 「鳥總立」(芸術院賞、恩賜賞)、 近刊「落人の家」
- 文庫
- 「前登志夫歌集」、 「存在の秋」(講談社文芸文庫)
- エッセイ集
- 「吉野紀行」(角川書店)、 「吉野日記」(角川書店)、 「存在の秋」(小沢書店)、 「大和の古道」(講談社)、 「樹下三界」(角川書店)、 「吉野遊行抄」(角川書店)、 「吉野鳥雲抄」(角川書店)、 「吉野風日抄」(角川書店)、 「吉野山河抄」(角川書店)、 「木々の声」(角川書店)、 「病猪の散歩」(NHK出版)
- 評論集
- 「山河慟哭」(朝日新聞社)、 「明るき寂寥」(岩波書店)、 「歌のコスモロジー」(本阿弥書店)、 「万葉びとの歌ごころ」(NHK出版)
- 短編集
- 「森の時間」(新潮社)
図書館劇場 Ⅱ(県立図書情報館館長公開講座)第二幕
- 主催
- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会
- 日時
- 平成19年7月28日(土) 13:00 〜 16:00
- 会場
- 1階 交流ホール
- テーマ
- 「役小角と修験道」 (えんのおづぬとしゅげんどう)
- プログラム
-
- 「道教と修験道」 千田 稔(当館館長)
- 朗読 :「山本ひろ子著『大荒神頌(だいこうじんしょう)』より」 都築 由美氏(アナウンサー)
- 「役行者と世界遺産」 田中 利典氏 (金峯山修験本宗 総本山金峯山寺 宗務総長・執行長)
- 参加者数
- 約200名


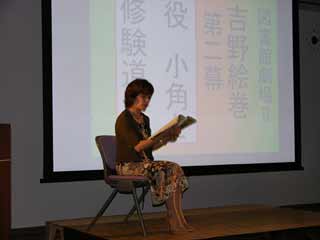


田中 利典 (たなか りてん)
1955年 京都府綾部市に生まれ、1970年、金峯山寺にて得度受戒。
1979年 龍谷大学文学部仏教学科卒業。
1981年 叡山学院専修科卒業、総本山金峯山寺奉職。
1993年 一千座護摩供修行 満行。
1994年〜2001年 金峯山修験本宗教学部長・総本山金峯山寺執行。
1995年〜 日本山岳修験学会評議員。
1996年〜2003年 全日本仏教青年会副理事長。
2001年〜 金峯山修験本宗宗務総長・総本山金峯山寺執行長。
2001年〜 全日本仏教会評議員・国際交流協会評議員。
2001年〜 宗教法人林南院住職。
2004年〜 吉野ユネスコ協会副会長
- 著書
-
- 『吉野薫風抄−修験道に想う』(金峯山時報社刊)
- 『修験道修行大系』(共著 国書刊行会刊)
- 『葬式仏教は死なない』(共著。白馬社刊)
- 『修験道っておもしろい』(白馬社刊)など。
図書館劇場 Ⅱ(県立図書情報館館長公開講座)第一幕
- 主催
- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会
- 日時
- 平成19年5月26日(土) 13:00〜16:00 (開場12:00〜)
- 会場
- 1階 交流ホール
- テーマ
- 「飛鳥と吉野 −吉野宮−」
- プログラム
-
- 「天武・持統天皇と吉野宮」 千田 稔(当館館長)
- 朗読 :「梨木香歩(なしき かほ)『丹生都比売(におつひめ)』より」 都築 由美氏(アナウンサー)
- 「万葉集のなかの吉野」 井上 さやか氏 (奈良県立万葉文化館古代学研究所主任研究員)
- 参加者数
- 約200名

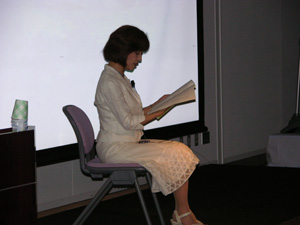

井上 さやか (いのうえ さやか)
1971年、宮崎県生まれ。中京大学大学院博士後期過程満期退学。文学博士。中京大学教養部非常勤講師などを経て、現職(奈良県立万葉文化館古代学研究所主任研究員)。 専門分野は万葉集を中心とした上代文学。
- 著書
-
- 『天平万葉論』 共著(翰林書房)
- 『高市黒人・山部赤人 人と作品』 共著(おうふう)
- 『万葉ことば事典』(大和書房)
- 『セミナー万葉の歌人と作品』7巻、 12巻(和泉書院)など