玉井家記録「庁中漫録」について |
|
|
| |
奈良文化女子短期大学教授 廣吉 壽彦 |
玉井家記録は、通称広義で「庁中漫録」といい全78巻から構成される(高田十郎著『奈良百話』所収ほか)。近世後期、奈良奉行所の与力玉井家で整理し通巻番号を与えたもので、題箋にみえる書名と内題で異なるものも若干ある。その大部分は玉井与右衛門定時が在勤中の記録や職務遂行に伴い筆写したり、退任後編術したものである。
庁中漫録の庁中とは唐風の呼称、奈良(京都の北京に対し南京<ナンケイ>)、町奉行所(尹市<インシ>)、すなわち南京尹市(奈良奉行所)在勤中の与力玉井家歴代の当主が仕事にかかわって作成したものとの意であろう。定時の命名と考えられる。
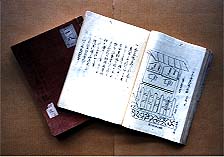 玉井定時(1646〜1720)は、幼名十兵衛・亀之助、以長斎と号した。若い頃は郡山藩士で、延宝8(1680)年父井関六大夫の隠居に伴い奈良奉行所の与力職を継いだ人である。
玉井定時(1646〜1720)は、幼名十兵衛・亀之助、以長斎と号した。若い頃は郡山藩士で、延宝8(1680)年父井関六大夫の隠居に伴い奈良奉行所の与力職を継いだ人である。
奈良奉行所は、慶長18(1615)年江戸幕府が遠国奉行の一つとして創設したもので、主に南都の町政や大和国内の社寺行政を担当、大和武士の出である中坊秀政が起用された。2代目奉行中坊時祐は慶安2(1649)年南都での両神事を満足につとめるには与力・同心が必要だと幕府に奏請して長崎奉行所並みに150石取り与力6騎、同心30名(7石2人扶持)を預けられ、このとき父六大夫が与力に取り立てられ、多門山麓に邸宅が与えられた。たまたま定時の代、天和2(1682)年奈
良奉行に大関勘右衛門増公が着任、翌年改姓を命じられ、玉井姓となった。姓のうちに"関"があったからである(巻25)。
全78巻の内容を通覧し解説することは紙数の関係からも到底不可能だから独断だが興味深いものの紹介にとどめたい。全巻を分類すると
- 玉井定時の在任中職務に基づき事前調査や職務遂行の経緯を明らかにするもの
- 定時の職務執行のうえで必携としたもの
- 定時が退任後、興味のおもむくまま大和・南都について編術した地誌のたぐい
- 定時が筆写した戦記その他文学作品など
- 定時の末裔の記録・筆写のたぐい
などに纏めることができよう。
1.では歴代奈良奉行は着任直後に管内の主要社寺を巡見するならわしで「遠方寺社巡見記」(巻49)は、その随行記。また南都には幕吏の下向も多い。その準備、調査、案内随行の記録として「所司代松平紀伊守殿南都御越記録」(巻60)「上使本庄安芸守殿春日御代参記録」(巻57)「若年寄稲垣対馬守其外南都御越記録」(巻58)のほか幕命で天皇陵の調査、周垣事業に従った「元禄十丁丑年山陵記録」(巻53)、「大仏殿再建記」全2巻(巻43・44)、正倉院の「御開封記」(巻45)などがある。
2.には狭義の「庁中漫録」全8巻(巻22〜29)は奉行所の布令(触・覚など)や「薪能番組」全2巻(巻40・41)のほか執務必携ともいうべき「官補補略」全3巻(巻61〜63)、「士官愚聞抄」(巻66)、「里程大和国著聞記」(巻20)、「諸国城主注録」(巻70)などがある。
3.には「大和名勝志」全16(巻1〜16)や「奈良街著聞記」(巻19)は、大和・南都に関する地誌でこの編述に用いた史料に「大和国著聞記」全3巻(巻17〜19)などがある。全78巻のうちでも白眉のもので生涯かけて編述しただけに、正確を記し、病没直前まで頭注として補筆がある。詳述できないが、現在亡失した南都の一部の町の検地帳や屋地子帳の筆写も含む。興味ある方は筆者監修の『江戸時代人づくり風土記−29
奈良』(農山漁村文化協会 1998)の巻末に「江戸時代奈良の主な文献資料」として解説を施しておいた。従来の霊験あらたかな社寺の案内記、あるいは主要な社寺や史跡の由来や縁起、歌枕に出る名所・史跡を若干の詩歌を援用した名所記・地誌をこえるもので奈良県内の地方史編纂、とりわけ近世の初期・中期の考察には欠くことのできない基本資料といっても過言でなかろう。
4.には「難波戦記」(巻68)「大坂記」(巻69)の戦記や「明月記」(巻71)「源氏口伝・一条禅閣御説」(巻72)などもある。また定時の後裔が「以長翁親墨冨士野往来帖」(巻76)のように題名を与えた筆写本も含まれている。
5.には「春日若宮祭礼御仮屋竹木代」(巻37)「春日御仮屋竹木松葉代廻帳」(巻38)は定時の嫡子与市右衛門や与力斎藤甚右衛門の職務執行に伴うもの、「元文式御定書」(巻77)は玉井定央の筆写、「後素記・執礼秘書」(巻50)は定時の筆写であるが、玉井定孝が補修した奥書をもつ。「年中行事」(巻78)は近世後期の与力家の年中行事に伴う献立等をうかがう貴重な記録である。
全巻を通じ10丁に充たないものもある反面200丁をこえる大冊もある。昭和44年8月4日から同月30日にかけてマイクロフィルムに収め研究者の利用に供せられた県立奈良図書館の労に感謝する共にせめても地誌類の活字化がはかられることを祈るものである。
※なお、同文書は平成10年9月、奈良市教育委員会文化財課の協力をえて当館に寄託され、郷土資料室で保管している。
|目次に戻る| |次へ|
奈良県立奈良図書館「芸亭」
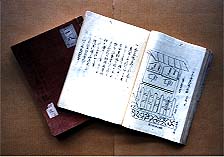 玉井定時(1646〜1720)は、幼名十兵衛・亀之助、以長斎と号した。若い頃は郡山藩士で、延宝8(1680)年父井関六大夫の隠居に伴い奈良奉行所の与力職を継いだ人である。
玉井定時(1646〜1720)は、幼名十兵衛・亀之助、以長斎と号した。若い頃は郡山藩士で、延宝8(1680)年父井関六大夫の隠居に伴い奈良奉行所の与力職を継いだ人である。