過去の図書館劇場(平成22年度)(県立図書情報館館長公開講座)
図書情報館では、千田 稔館長の公開講座を「図書館劇場」と銘打ち、これまで、東アジアにおける平城京の先進性を、また、神仙境・吉野の果たした役割を、
さらに、昨年度は、『奈良は美味いものばかり』をメインテーマとして、我が国の食卓を彩る多くがここ奈良で育まれたこと、
また今に伝えられる奈良の酒食文化を明らかにしてきました。
平城遷都1300年を迎えた今年度は、『平城京をめぐる群像』をメインテーマに、人物に焦点をあて、平城京とその時代の姿を探ります。
なお、本公開講座は毎回、奇数月の第4土曜日の 13:00〜16:00 に開催します。
- 図書館劇場Ⅴ(県立図書情報館館長公開講座) 第6幕
- 図書館劇場Ⅴ(県立図書情報館館長公開講座) 第5幕
- 図書館劇場Ⅴ(県立図書情報館館長公開講座) 第4幕
- 図書館劇場Ⅴ(県立図書情報館館長公開講座) 第3幕
- 図書館劇場Ⅴ(県立図書情報館館長公開講座) 第2幕
- 図書館劇場Ⅴ(県立図書情報館館長公開講座) 第1幕
図書館劇場Ⅴ(県立図書情報館館長公開講座)第6幕 [終了]
終了しました。多数のご参加ありがとうございました。
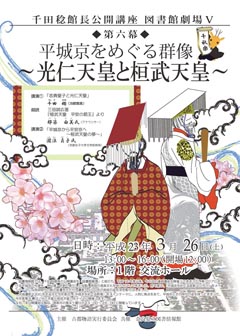
画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、1.4MB]
- 日時
- 平成23年3月26日(土) 13:00 〜 16:00 (開場 12:00)
- 会場
- 1階 交流ホール
- テーマ
- 光仁天皇と桓武天皇
- プログラム
-
- 講演① 「志貴皇子と光仁天皇」 千田 稔(当館館長)
- 朗読 三田誠広著『桓武天皇 平安の覇王』より 都築 由美氏(アナウンサー)
- 講演② 「平城京から平安京へ〜桓武天皇の夢〜」 瀧浪 貞子(たきなみ さだこ)氏 (京都女子大学文学部教授)



- 参加者数
- 約350名
- 参加料
- 参加料(資料代等)としてお一人様500円を当日受付にて徴収します。
- 主催
- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会
- 問合せ先
-
〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地
奈良県立図書情報館 「図書館劇場Ⅴ第6幕」担当
TEL 0742-34-2111
FAX 0742-34-2777
瀧浪 貞子 (たきなみ さだこ)
1947年(昭和22年)大阪府生まれ。
1973年京都女子大学大学院修士課程修了。京都女子大学文学部教授。文学博士。専門は日本古代史。
NHK講座「歴史で見る日本」で飛鳥〜平安時代を担当(1989年〜94年)
- 主な著書
-
- 『日本古代宮廷社会の研究』(思文閣出版)
- 『平安建都』(集英社)
- 『最後の女帝 孝謙天皇』(吉川弘文館)
- 『帝王聖武 天平の勁き皇帝』(講談社)
- 『女性天皇』(集英社新書)など
図書館劇場Ⅴ(県立図書情報館館長公開講座)第5幕 [終了]
終了しました。多数のご参加ありがとうございました。
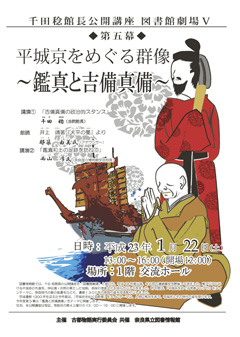
画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、1.2MB]
- 日時
- 平成23年1月22日(土) 13:00 〜 16:00 (開場 12:00)
- 会場
- 1階 交流ホール
- テーマ
- 鑑真と吉備真備
- プログラム
-
- 講演① 「吉備真備の政治的スタンス」 千田 稔(当館館長)
- 朗読 井上靖著『天平の甍』より 都築 由美氏(アナウンサー)
- 講演② 「鑑真和上の足跡を訪ねて」 西山 厚(にしやま あつし)氏 (奈良国立博物館学芸部長)



- 参加者数
- 約350名
- 参加料
- 参加料(資料代等)としてお一人様500円を当日受付にて徴収します。
- 主催
- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会
- 問合せ先
-
〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地
奈良県立図書情報館 「図書館劇場Ⅴ第5幕」担当
TEL 0742-34-2111
FAX 0742-34-2777
西山 厚(にしやま あつし)
奈良国立博物館学芸部長。
昭和28 年、徳島県鳴門市生まれの伊勢育ち。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。
「女性と仏教」など数々の特別展を企画。
仏教を中心にして、日本の歴史・思想・文学・美術を総合的に見つめ、思い、書き、生きた言葉で語る活動を続けている。
図書館劇場Ⅴ(県立図書情報館館長公開講座)第4幕 [終了]
終了しました。多数のご参加ありがとうございました。
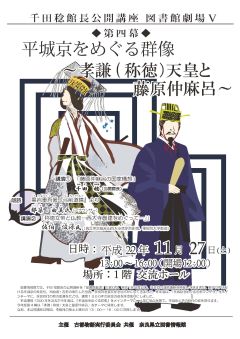
画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、2.6MB]
- 日時
- 平成22年11月27日(土) 13:00 〜 16:00 (開場 12:00)
- 会場
- 1階 交流ホール
- テーマ
- 孝謙天皇(称徳天皇)と藤原仲麻呂
- プログラム
-
- 講演① 「藤原仲麻呂の国家構想」 千田 稔(当館館長)
- 朗読 黒岩重吾著『弓削道鏡』より 都築 由美氏(アナウンサー)
- 講演② 「称徳女帝と仏教―西大寺創建をめぐって―」 佐伯 俊源(さえき しゅんげん)氏 (種智院大学人文学部教授。真言律宗総本山西大寺清浄院住職。)



- 参加者数
- 約300名
- 参加料
- 参加料(資料代等)としてお一人様500円を当日受付にて徴収します。
- 主催
- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会
- 問合せ先
-
〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地
奈良県立図書情報館 「図書館劇場Ⅴ第4幕」担当
TEL 0742-34-2111
FAX 0742-34-2777
佐伯 俊源(さえき しゅんげん)
1965年奈良市生まれ。東京大学大学院(修士課程)終了。種智院大学人文学部教授。真言律宗総本山西大寺清浄院住職。
専門分野は、日本仏教史、仏教福祉学。特に近年は戒律・密教・福祉の視点から日本仏教を捉え直す作業を進めている。
- 主な著書・論文
-
- 「叡尊上人と真言密教―「冥受三摩耶戒灌頂印信」をめぐって―」
- 『マンダラの諸相と文化 : 頼富本宏博士還暦記念論文集』(法蔵館 2005年)
- 『戦後仏教社会福祉事業の歴史的展開』(共著 法蔵館 2007年)
図書館劇場Ⅴ(県立図書情報館館長公開講座)第3幕 [終了]
終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、2.4MB]
- 日時
- 平成22年9月25日(土) 13:00 〜 16:00 (開場 12:00)
- 会場
- 1階 交流ホール
- テーマ
- 聖武天皇と光明皇后
- プログラム



- 参加者数
- 約350名
- 参加料
- 参加料(資料代等)としてお一人様500円を当日受付にて徴収します。
- 主催
- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会
- 問合せ先
-
〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地
奈良県立図書情報館 「図書館劇場Ⅴ第3幕」担当
TEL 0742-34-2111
FAX 0742-34-2777
馬場 基(ばば はじめ)
1972年、東京都に生まれる。1995年、東京大学文学部卒業。
2000年、東京大学大学院博士課程中退。現在、奈良文化財研究所都城発掘調査部主任研究員。
- 主な編著書
-
- 「駅と伝と伝馬の構造」(『史学雑誌 105編3号』 1986年)
- 「「都市」平城京の多様性と限界」」『年報都市史研究 13』 2005年)
- 「上咋麻呂状と奈良時代の官人社会」 (『奈良史学 23号』 2006年)
- 「平城京に暮らす : 天平びとの泣き笑い」(吉川弘文館 2010年)
図書館劇場Ⅴ(県立図書情報館館長公開講座)第2幕 [終了]
終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、1.9MB]
- 日時
- 平成22年7月24日(土) 13:00 〜 16:00 (開場 12:00)
- 会場
- 1階 交流ホール
- テーマ
- 平城京をめぐる群像
- 〜長屋王と行基〜
- プログラム
-
- 講演① 「行基の実像と虚像」 千田 稔(当館館長)
- 朗読 深谷忠記著『迷界流転「長屋王の変」異聞』より 都築 由美氏(アナウンサー)
- 講演② 「長屋王とその周辺」 舘野 和己氏(奈良女子大学文学部教授)



- 参加者数
- 約370名
- 参加料
- 参加料(資料代等)としてお一人様500円を当日受付にて徴収します。
- 主催
- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会
- 問合せ先
-
〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地
奈良県立図書情報館 「図書館劇場Ⅴ第2幕」担当
TEL 0742-34-2111
FAX 0742-34-2777
舘野 和己(たての かずみ)
昭和25(1950)年11月 東京に生まれ、昭和49(1974)年3月 京都大学文学部史学科を卒業。昭和55(1980)年3月 京都大学大学院 文学研究科博士後期課程単位取得満期退学した後、昭和59(1984)年1月 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部史料調査室に入所。 昭和62(1987)年10月から平成2(1990) 年3月まで奈良市教育委員会社会教育部文化課長となり、平成2(1990)年4月から奈良国立文化財研究所 平城宮跡発掘調査部主任研究官、平成5(1993)年4月からは同上調査部史料調査室長、平成11(1999)年4月から平成13(2001) 年3月まで 奈良女子大学大学院人間文化研究科併任教授、そして平成13(2001)年4月より奈良女子大学文学部教授就任し、現在に至る。
- 主な著書・論文
-
- 『日本古代の交通と社会』(塙書房 1998年)
- 『古代都市平城京の世界 (日本史リブレット:7)』(山川出版社 2001年)
- 『木簡 : 古代からのメッセージ』(共著 大修館書店 1998年)
- 「天武天皇の都城構想」 栄原永遠男・西山良平・吉川真司編 『律令国家史論集』(塙書房 2010年)
- 「都のある空間 平城京域」 文学部なら学プロジェクト編 『奈良ガイド : こだわりの歩き方』(昭和堂 2009年)
- 「古代都城の成立過程」 舘野和己編 『古代都城のかたち』(同成社 2009年)
- 「若狭・越前の塩と贄」『日本海域歴史大系1』古代篇1(清文堂 2005年)
- 「ヤマト王権の列島支配」『東アジアにおける国家の形成 (日本史講座:第1巻)』(東京大学出版会 2004年)
- 「古代都市の実像」『律令国家と天平文化 (日本の時代史:4)』(吉川弘文館 2002年)
- 「木簡の表記と記紀」『國語と國文學 936』(2001年)
図書館劇場Ⅴ(県立図書情報館館長公開講座)第1幕 [終了]
終了しました。多数のご参加ありがとうございました。
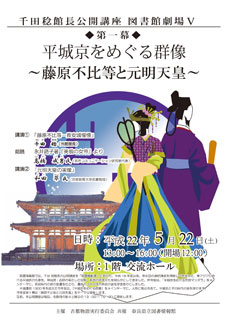
画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、1.3MB]
- 日時
- 平成22年5月22日(土) 13:00 〜 16:00 (開場 12:00)
- 会場
- 1階 交流ホール
- テーマ
- 平城京をめぐる群像
- 〜藤原不比等と元明天皇〜
- プログラム




- 参加者数
- 約350名
- 参加料
- 参加料(資料代等)としてお一人様500円を当日受付にて徴収します。
- 主催
- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会
- 問合せ先
-
〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地
奈良県立図書情報館 「図書館劇場Ⅴ第1幕」担当
TEL 0742-34-2111
FAX 0742-34-2777
和田 萃 (わだ あつむ)
京都教育大学名誉教授、奈良県立橿原考古学研究所指導研究員。
昭和19年、中国東北部(旧満州国遼陽市)で生まれ、生後間もなく奈良県田原本町に移り住み、大和の歴史的風土のなかで育つ。現在、高取町吉備に在住。
昭和47年、京都大学大学院(国史学専攻)博士課程修了。京都大学文学部助手をへて、京都教育大学に勤務。昭和63年に教授。京都大学博士(文学)。
平成19年3月、定年退官。
日本古代史を専攻し、日本古代の思想や文化、木簡などを研究。昭和47年以来、奈良県立橿原考古学研究所の所員として、日本古代史と考古学との接点を
埋める研究活動を行っている。吉野在住の歌人、故前登志夫氏に師事し、ヤママユ同人。
現在、産経新聞朝刊(月曜日の奈良版)に、「やまと歴史探訪」を掲載中。
- 主な著書
-
- 『大系 日本の歴史 2 古墳の時代』(小学館)
- 『日本古代の儀礼と祭祀・信仰』上・中・下巻(塙書房)
- 『飛鳥−歴史と風土を歩く−』(岩波新書)
- 編著
-
- 『大神と石上』
- 『熊野権現』(ともに筑摩書房)
- 『古代を考える 山辺の道』(吉川弘文館)
- 共編著
他に論文多数。
第2期「図書館劇場友の会」ご案内
「図書館劇場友の会」の募集は終了しました。
平成18年5月からの開催以来、多数の方にご参加いただいております、千田稔館長公開講座「図書館劇場」。 今年度第2期「図書館劇場友の会」会員を募集します。平城遷都1300年を迎え、奈良時代からの都の変遷をたどり 遷都1300年の奈良の姿を千田館長はじめ、多彩なゲスト講師の講座と都築由美さんの朗読により浮き彫りにする図書館劇場、 皆様のご参加・ご入会を心よりお待ち申し上げております。
- 特典
-
- 図書館劇場(全6回)に、お申込みなくご参加いただけます。(各回の資料代は不要です。)
- 会員には、会員証を発行します(1年度間有効)。
- 「図書情報館イベント情報」をお届けします。
- 館長を交えた、会員限定「館長文化サロン」に参加することができます。 (食事会となった場合、お食事代金等は実費となります。)
- 年会費
- 3,000円(年度途中にご入会の場合でも同額となります。)
※一旦納入された会費はご返金いたしかねます。 - お申込み方法
- 募集は終了しました。
- 2階貸出・返却カウンターにて会費を添えて申込みください(会員証は後日送付します)。 FAX、メールにてお申込みいただき、会費を下記にお振込ください。お振込確認後に会員証を送付します。 なお、誠に恐縮ですが、振込等にかかる手数料は、お申込み者のご負担でお願いします。
- (銀行振込) 南都銀行大宮支店 普通 0587502
古都物語実行委員会委員長
奈良県立図書情報館 館長 千田 稔
(郵便振替) 加入者名:古都物語実行委員会
口座番号:00940-2-280620

図書館劇場への参加は、これまでどおり各回ごとの参加も受付けています。(当日資料代1人500円)
第2幕以降のテーマ(予定)
- 7/24 第2幕 長屋王と行基
- 9/25 第3幕 聖武天皇と光明皇后
- 11/27 第4幕 孝謙(称徳)天皇と藤原仲麻呂
- 1/22 第5幕 鑑真と吉備真備
- 3/26 第6幕 光仁天皇と桓武天皇